| 刀水歴史全書80 | |
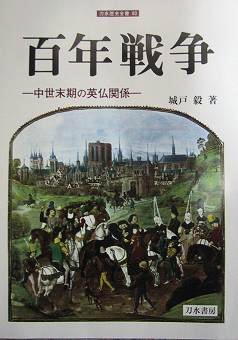 |
百年戦争 中世末期の英仏関係 城戸 毅著 定価: 本体3000円+税 2010年05月刊 ISBN978-4-88708-379-0 四六判 373頁 在庫あり |
| 百年戦争の“全体像”が時代の中に浮かび上がる!
今まで我が国にまとまった研究がなく,欧米における理解からずれていたこのテーマ。英仏関係および,フランスの領邦君主諸侯間の関係をとおして,戦争の前史から結末までを描いた,本邦初の本格的百年戦争の全体像 |
|
| 刀水歴史全書80 | |
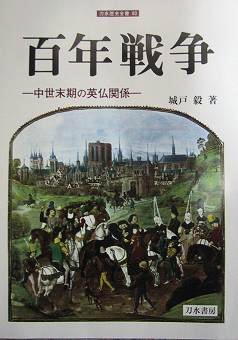 |
百年戦争 中世末期の英仏関係 城戸 毅著 定価: 本体3000円+税 2010年05月刊 ISBN978-4-88708-379-0 四六判 373頁 在庫あり |
| 百年戦争の“全体像”が時代の中に浮かび上がる!
今まで我が国にまとまった研究がなく,欧米における理解からずれていたこのテーマ。英仏関係および,フランスの領邦君主諸侯間の関係をとおして,戦争の前史から結末までを描いた,本邦初の本格的百年戦争の全体像 |
|
| 【目次】 | |
| 第一章 前史と前半期(一四世紀) 1 前史 2 開戦前後 3 失われた平和の機会(1)ブレティニ‐カレーの和 4 失われた平和の機会(2)レウリンゲン休戦協定 第二章 後半期に先だつ状況変化 5 フランス王室の内輪もめとフランスの政治的分裂 6 フランス王族の内紛のイングランドへの影響 7 英仏両国における状況変化 8 開戦に至る英仏交渉 第三章 後半期の推移―イギリスのノルマンディ占領統治を中心に 9 ヘンリ五世のノルマンディ遠征からトロア条約まで 10 ノルマンディの占領統治 11 英軍占領下ノルマンディの身分制議会 12 イギリス占領当局の土地政策=植民政策 13 占領当局の治安対策―住民鎮撫と軍の規律 14 ノルマンディ住民の帰属感情 15 イングランドとノルマンディ喪失の危機 第四章 戦争の終結に向って―イギリス‐ブルゴーニュ関係の変容 16 アラス和議(一四三五年) 17 イギリス‐ブルゴーニュ関係の変容 終 章 |
|
| 【書 評】 | |
『史学雑誌』第121編第10号 2012年10月 書評より 評者:堀越宏一 百年戦争とは、ヨーロッパの歴史のなかに屹立するひとつの巨大な山脈である。1330年代に始まり、15世紀半ばに終わる過程で、当事者である英仏両王国の国制は大きく転換し、それが始まった時には封建制が支配していた社会が、終結時には絶対王政的な社会に姿を変えていた。近年、ヨーロッパのさまざまな国と地域が営む歴史的営為が、統一的モデルよりも多様性のうちに考究される傾向にあっても、中世ヨーロッパ文明という共通の視点に立つならば、英仏両王国の規範的モデルとしての位置づけは否定しようもない。その意味でも、両王国の14・15世紀を支配した百年戦争の歴史的意義はまことに大きい。(略)1世紀以上の期間に及ぶ、このような巨大な歴史的変化の全体を論じるためには、いったい幾冊の浩瀚な書物が必要になるのだろうか。中世後期とも呼ばれるこの時代のヨーロッパを深く理解しようとする者にとって、百年戦争の全体像を知ることは、その生涯を傾けるほどの知的努力が求められる課題であり続けている。そのような百年戦争に関する知的営為のなかで、城戸毅が2010年に著した『百年戦争』という書物では、「まえがき」において、執筆の枠組みとして、百年戦争についてのイングラドからの観点が優越すること、そして、「本書は、・・・戦史ではなく、戦争の政治的環境の解明をめざしたものなので、そうした環境がイギリス側からみてどのようなものだったのか、英語圏の研究ではどう説かれているか、の紹介に重点をおいている」(4頁) ことが表明される。若干拡大して言えば、英仏間の政治外交史的文脈を山脈の主稜と見定め、そのイングランド側の側面を中心として論じることで、この山脈の全体をたどることを目指した成果である。そして、これまで日本語で書かれた百年戦争論のなかで、百年戦争の全体を専門研究のレヴェルで見通すことを可能にした初めての書物となった。この書評の結論は、このことに尽きている。(中略)そのうえで、本書を総合的に見るならば、やはり、長い研究の歳月を積み重ねてきた著者ではないと出会えない文章に行き当たり、刮目させられることが多かった。シャルル6世期のフランス国内分裂とイングランドのバラ戦争に共通点が多いという記述(318頁の註)は、英仏両国の歴史を深く知る者でなければなしえない発言であり、当該分野における比較史的展望を提示している。また、ノルマンディー占領統治において用いられた、封建制的な軍役奉仕義務をともなう所領分配が、征服者集団が軍事力を確保するための効果的な方法であることの指摘(161〜162頁)や、15世紀イングランド王国について、国益に矛盾するようなグロスタ公ハンフリの利己的行動を止められない、当時の国家の実態と限界(260頁)への言及は、私たちに、百年戦争を超えたより大きな問題を考えるヒントを与えてくれているのである。 『歴史学研究』 2012年2月 第889号 城戸毅氏は,『マグナ・カルタの世紀』(東京大学出版会,1980年)や『中世イギリス財政史研究』(東京大学出版会,1994年)などで知られるイギリス中世史の重鎮である。その著者も指摘するように,百年戦争に関するわが国の歴史研究は,新書レヴェルの概論にとどまっている。(略)これに対して,本書は百年戦争に関する本邦初の本格的研究であり,第三章の一部をのぞき,大部分が書き下ろしである。(中略)まえがきによると,本書は決して百年戦争の“戦史”ではない。本書は,フランス史の文脈で説かれることの多い百年戦争を「イギリス側からみるとどう見えたか」を中心に,「戦争の政治的環境の解明をめざしたもの」である。(4頁)。そのうえで,序章では1337〜1453年を“百年戦争”とする歴史観の形成過程を検討したのち,本編では英・仏王権およびフランス諸侯層の関係を,時系列にそって,とくに「戦争の曲がり角となった重要な政治環境の変化」(4頁)に重点をおきつつ叙述していく。(以下略)まえがきから察するに,著者は『マグナ・カルタの世紀』の執筆当時から,13世紀はもちろん,その後の英仏関係の展開に関する本書の構想を練られていたと考えられる。そうであれば,本書は著者の30年以上に及ぶ研究成果の集大成といえ,それは,百年戦争勃発の原因そのものといえる英・仏王権の権力関係の変遷を,ひとつひとつ詳細に解明してきた軌跡といえる。その成果は,わが国学界における百年戦争の歴史像を格段に豊かにするものであり,同時に今後の本格的研究に大きなはずみをつけるものとなろう。本書を得た現在,われわれは近年における英仏双方の研究動向の統合に着手したうえで,百年戦争期の英仏関係論―相互浸透と分離の同時進行―をさらに深化させていくことを求められることとなった。このように評者自身をふくめた,わが国学界の今後の課題を確認し,書評を終えることとする。 評者:佐藤 猛 『西洋史学』No.241 城戸毅氏のこの書物は,概説書ではない。もともと特殊講義のための講義ノートであり,読者が百年戦争の経緯,この時代の英仏両国の政治史のアウトラインについて,それなりの知識を有していることが前提とされている。著者も序文で,戦史ではなく「戦争の環境の解明」「戦争の政治史」「重要な政治環境の変化の分析」に重点をおき,これまで日本ではあまり触れられてこなかったトピックを中心に論じたと述べている(略)。著者が重点をおいたトピックとして,第一に百年戦争の原因論がある。(略)第二の重点的なトピックは,15世紀におけるランカスター朝のノルマンディ占領と支配,それに対する住民の抵抗である。(略)しかし著者の考察の最大の焦点はノルマンディ住民の帰属感情に当てられている。当局に武力で抵抗したブリガンと呼ばれる匪賊たちの問題がその手がかりとなる。フランスの歴史学では伝統的にこのブリガンたちをアルマニャック派のパルチザンと捉えてきたのに対し,イギリスでは彼らはおおむね盗賊など反社会的犯罪者と見なされてきた。著者は近代的な国民意識を前提とすることは極力避けつつ,慎重にブリガンの実態を追っていく。(略)このブリガンについての分析はきわめて説得的であり,前近代において外民族支配に直面した民衆の意識についてのより広い考察の手がかりとなるものである。この他に著者は,日本ではこれまで詳しい解説がされてこなかった二つのトピックに力点をおいて紹介している。いずれもイギリス―ブルゴーニュ関係に係わるもので,ひとつはアラスの和議であり,もうひとつは両国の政治的・経済的関係である。(略)ともあれ,この複雑な戦争の諸側面について,信頼性の高い手引き書が現れたことを喜びたい。 評者:江川 温 『図書新聞』 2010.8.14 書評より “ヨーロッパにおける国家,政治構造の転換の象徴” ・・・[前略]・・・ 本書は,必ずしもわが国では詳細に知られているわけではない英仏間の百年戦争に関する本格的な論考である。通例,流布されているイングランド王のフランス王位請求を起点とした王位継承戦争という見方を著者は直接的にはとらない。もっと複眼的な視座を通して,多様な領地権並びに王権をめぐる権益を浮き彫りにして,ある種の中世ヨーロッパ国家像の一端を抽出していく。つまり,「戦史ではなく,戦争の政治史,海峡を挟んだイングランドとフランスおよびフランスの領邦君主諸侯の間の関係史」(「まえがき」)を主軸として論及する本書は,微細にわたり領邦君主諸侯の動態を追っているのだ。・・・(略)・・・著者の論点は,なぜ,百年以上という長きにわたり戦争が泥沼化していったかということだ。その核心は,現在では地域圏のひとつであり,ワインの産地として有名なブルゴーニュが公国のひとつとしてフランス王国と対峙し,イングランド王国と連携していたことに求められる。・・・(略)・・・著者は,「フランスに最後まで残っていたこれら大領邦(引用者註=ブルゴーニュ) の消滅は,イギリス王のフランスへの介入の口実と成功の見込みを消滅させた」と述べ,百年戦争の終焉へ至る道筋を明らかにしていく。百年戦争はある意味,ヨーロッパにおける国家並びに政治構造の転換を示した象徴的な“事件”だったということになる。 (評者:植田 隆) 出版ニュース』 2010年7月中旬号 書評より 前略・・・著者は,中世後期のイギリス史を学んでいく過程で,英仏両国の関係史に理解を深めたことがこの研究につながった。ここでは,戦争の原因や解明という観点から,長引いた理由,王権の力量増大の意味,両国に与えた政治的影響まで,戦争の政治史をトータルに描きだす。西洋史学の新たな境地といえる労作。 『エコノミスト』2010年6月15日号 「歴史書の棚」より “イギリスから見た百年戦争の全体像” 前略・・・これまで百年戦争はフランスの側から語られることが多かった。しかし,イギリス中世史の大家である著者は対岸側から見ることで,百年戦争の全体像を描き出す。・・・中略・・・むしろ注目されるのは,百年戦争の経過のなかで,英仏両国の国民意識が形成されたことだ。しばしば引き合いに出されるジャンヌ・ダルクだが,その歴史像には近代的解釈と愛国主義的偏向が甚だしいという。 ところで,英軍占領下のノルマンディーで治安が悪かったことは衆目が認めている。治安撹乱者としてしばしば登場するのがブリガンと呼ばれる盗賊であった。その実態が反社会的な盗賊にすぎなかったのか,それとも征服者に服従しない確信犯ゲリラであったのか。なるほど,戦争の混乱も行政機構の崩壊も無法な略奪者の群れを生み出しやすい。印象深いのは,実証的な手続きでブリガンを支援する広範な民衆の感情が鮮明になるところだ。・・・後略・・・ 評者:本村凌二 |
|
|
|
|
| HOME | 会社案内 | 近刊案内 | 書名一覧・索引 | 注文について | リンク集 |
| Copyright (c) 2005 Tosui Shobo, Publishers & Co., Ltd. All Rights Reserved |